
4-4-2とはサッカーにおいて最も基本的なフォーメーションである。なぜなら全てのフォーメーションが4-4-2の足し算と引き算で語ることができるからである。
例えば、日本代表をカタールワールドカップベスト16に導いた3-4-3は4-4-2のバックラインの1人を2トップに持っていったものであるし、FC東京の基本フォーメーション4-3-3は中盤の4人の1人を前線に追加で配置した形である。
今回のガンバ大阪VSFC東京戦を見ていたサポーターはわかるだろうが、FC東京は攻撃時には4-3-3、守備時は4-4-2に可変していた。そして、後半には完全に4-4-2にフォーメーションを変えて挑んだ。しかし、結果は3-0での敗戦、しかもシュートはたった1本であった。
何がいけなかったのだろうか。今回は、FC東京の敗戦を参考に語っていきたい。
[原因.1] バイタルエリアの距離感
まず、1つ目の要因としては「バイタルエリアの距離感」にあったと考える。ここで、バイタルエリアって何?距離感って?となる人もいると思う。
1.バイタルエリア
バイタルエリアとは、今回のFC東京のフォーメーション4-4-2の画像において、松木、塚川、青木、佐藤の中盤4人と長友、森重、木村、鈴木の4人の間のスペースを指す。

この、四角い箱が3つ隣り合っているように見えるこのスペースである。サッカーではこのスペースでボールを相手より長く保持したいし、このスペースでボールを保持できればミドルシュートやアシストにつながるパス、ドリブルで相手を抜きシュートなどのサッカーにおけるボールシーンのほとんどがこのエリアから発生する。
そのため、ポジショナルサッカー同士ではこのバイタルエリアの取り合いとなる。
今回のFC東京は、ほとんど相手のバイタルエリアでボールを保持できず。できたとしても、シュートで終われないパターンが多かった。一方のガンバ大阪は、FC東京からボール絵を奪ったのちに適切なビルドアップをしパスをつなぎ、バイタルエリアに侵入。シュートで終わるシーンが圧倒的に多く、パスでゴール前に送りチャンスを造ったりクロスを上げる選択やカッインからのシュート、ゴールに向けドリブルをしシュートなど多彩な攻撃を見せつけられた。
この差が21本のガンバ大阪のシュート対1本のFC東京のシュート数となった。
2. 距離感
バイタルエリアを自由にさせると、チャンスを造られやすくなるのがわかったがこの「距離感」がなぜ重要なのだろうか。
「距離感」とは選手同士の物理的に離れている距離であり、「選手個人」と「選手のライン」の2種類がある。
「選手個人」の距離とは、選手同士の距離であり今回のFC東京の守備ではもっと狭い距離感で一定に保ち(壁を作るイメージである)、右サイドに来たら右サイドに全体的に寄る。左サイドから攻めてきたら全体的に右サイドによるなどの連動が必要である。しかし、この試合ではFC東京の選手たちは、来た敵に合わせて個人で守備をしてしまい、自らスペースを作り出してしまうことが多かった。加えて、どんなに左右に振られてもついていかなくてはならないという忍耐力が求められる。
<左に来た時>

<右に来た時>

次に、「選手のライン」の距離について。これは、バイタルエリアを語ったときの選手の2列目(松木のライン)と3列目(長友のライン)の距離のことである。

このエリアが広くなりすぎるとバイタルエリアががら空きになり、危険を招く。しかし、近くなりすぎるとエリアのスペースのほとんどを相手に使わせることになるうえ、裏抜けの縦パスが通りやすくなったりなどマイナス面が出てくる。
そのため、適切な距離を一定に保ちゾーンで守らなくてはならないため安易に4-3-3のポジショナルサッカーには4-4-2は安易にやってはいけない。また、普段ポジショナルサッカーをやっているFC東京にとってはどうしても堅守速攻のフォーメーションになってしまう4-4-2は悪手であったといえる。
2. ポジショナルプレーと浮くアンカー
アルベル政権のFC東京は、ポジショナルプレーと掲げている。これはガンバ大阪も同じである。まず、ポジショナルプレーとは何なのだろうか。
1. ポジショナルプレー
ポジショナルプレーは3つの優位的な特徴から構成されている。それは1.人数的優位 2.質的優位 3.位置的優位である。
1.人数的優位は数的優位とも呼ばれ、特定のエリア(攻撃時なら中盤やバイタルエリア、守備時なら自陣のバイタルエリアなど戦術により変わってくるが)に相手より多くの選手がいるようにすること。
2.質的優位とは、相手選手に対して相手より優れた自チームの選手が「1対1」の状況になるようにすること。
3.位置的優位は、ライン間やラインの裏に選手が適切な位置取りをし、ボール保持時にはスペースと時間(タメ)があるようにし、効果的に攻めることを指す(体の向きの調整なども含める)。
ポジショナルプレーを使うチームの選手は、以上の優位を作り出すことを常に意識してプレーしなければならない。
以上の特徴を、FC東京が考慮できていたかを考えたい。
人数的優位は、始終ボールはガンバ大阪に保持されクリアやパスをつないでもボールをまた取られ、攻撃チャンスをなかなか作らせてもらえなかった。
質的優位では、若手を多く起用したり長友が抜かれゴールを決めていたところを見る限り、作り出せていなかったと考えられる。
位置的優位は圧倒的にガンバ大阪の方がバイタルエリアでボールを保持し展開していたため、圧倒的に負けていたと考える。
これが、前半戦守備時また後半からフォーメーション変更した始終で起こっていた。
2. アンカー
次に、4-3-3で最重要といわれるアンカーに注目してみていきたい。

完璧に浮いている(フリーになっています)。一番展開に重要なアンカーを完璧に自由にさせてる。これに加えて、11番のジェバリがおりてきてダワンや山本に落とし展開に関与したり、アラーノ杉山に繋ぐことでプレーを潤滑させていた。また自分からドリブルで持って行ける選手であったので、FC東京側の守備は凄惨を極めた。
解決策
では、どうすればよかったのか。自分なりの意見を提案させていただく。
4-4-2(中盤ダイアモンド)

まずは、4-4-2中央ダイアモンド型(4-3-1-2)である。こうすることで展開で重要な中盤では相手のポジショナルプレーの重要な要素、人数優位をクリアでき、ジェバリへの縦パスも青木がいることでやすやすと出せなくなる。このことで、バイタルエリアでの位置的優位も潰せる。
しかし、問題はSB(サイドバック)が使い放題ではないかということだが、これもクリアできる。

SBに対して、IH(インサイドハーフ)が寄せることで、マークの受け渡しをしていくことでジェバリに対してCB(センターバック)をつけ警戒し、ウイングに対してはSBがつくことで相手の機能を停止させることができる。
攻撃は、中盤より上でボールをとりショートカウンターでよい。
4-5-1
2つ目は、4-5-1である。

こちらも、相手の1トップとアンカーをつぶしたうえで中盤で人数優位を作り出す。基本的には相手にボールを保持させるが、アダイウトンのラインを第1守備ラインとして、中盤にボールが入ってきたらそこを狙いにして奪う。
こちらも、攻撃はショートカウンターになる。しかし、2列目を連携させて全体的にラインを上げさせ、サイドバックが青木の横につければ2-3-5となりFC東京がいつもやっているポジショナルプレーとしての原則、数的、位置的優位がクリアでき、アダイウトンを起点に攻めることで質的優位も高い位置でクリアできるが、カウンターに気を付けなくなるが普段と変わらない攻撃ができチャンスを多く作れる点では、4-4-2中盤ダイアモンド型より価値にこだわっている現実的なフォーメーションであるといえる。
↓ポジショナルプレーを深く理解したい方へ↓
Coaches’ Voice | ポジショナル・プレー (coachesvoice.com)
↓4-4-2をもっと深く理解したい方へ↓

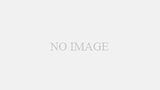

コメント